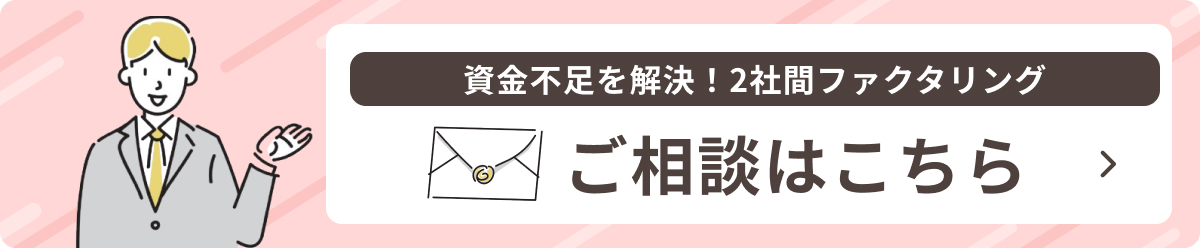神奈川県 食品加工業 創業46年
冷凍食品の製造工場では、日々の作業が止まることなく続いている。刻々と動くライン、寸分の狂いも許されない温度管理、徹底された衛生体制。その裏では、目に見えない経費の上昇が静かに、しかし確実に経営を締めつけている。
まず最初に圧迫しはじめたのは人件費である。最低賃金の上昇はすでに数年続いており、パートやアルバイトに依存する工程では、特にその影響が大きく表れている。機械化を検討する声もあるが、導入には大きな資本が必要となり、今のように現金の流れが細っている状況では容易には決断できない。
次に重くのしかかってきたのが、燃料費の高騰である。冷凍食品という業種の特性上、常に一定以下の温度を保つ必要があるため、電気代やガス代といったランニングコストは非常に大きなウェイトを占めている。エネルギーコストの変動がそのまま損益に直結するため、経費の予測が立てにくくなっている。
そこに円安の影響が加わる。海外から仕入れていた調味料や副材料の価格が軒並み上がり、従来と同じ原料を確保するだけでも仕入れ額が1.5倍近くになっているものもある。輸入に頼っていた包材も例外ではなく、コスト圧縮のために素材の見直しを迫られているが、安価な素材は破損や漏れのトラブルが多く、逆に返品やクレーム対応に追われるようになっている。
売上自体が落ちているわけではない。しかし、利益が残らない。販売価格にコスト上昇分をそのまま転嫁できればよいが、冷凍食品市場は価格競争が激しく、大手との価格差が購買行動に直結するため、簡単に値上げには踏み切れない。これまでも幾度か価格改定を試みたが、すぐに注文数が落ち込んだため、現状は限界まで踏みとどまっている。
こうした状況下で、資金繰りの調整手段として頼っているのがファクタリングである。製品を納品した後、代金の支払いまでには1〜2ヶ月のタイムラグがあるが、その間の資金がどうしても不足する。そのため、売掛債権を買い取ってもらい、先に資金化することで日々の運転資金を補っている。手数料は決して安くないが、工場の稼働を止めるわけにはいかない。材料がなければ製造はできず、人員も確保できない。
ファクタリングの利用は計画的に行っているものの、慢性的な資金不足を抜本的に解決するには至っていない。以前は銀行融資も検討したが、直近の決算書では収支が安定しておらず、審査は難航した。補助金や助成金の活用も視野に入れているが、申請には時間と労力がかかり、しかも確実に採択されるとは限らない。
製造ラインの一部自動化や、海外市場への販路開拓など、中長期的な対策案も浮かんではいる。だが、それらを実行に移すには、まずは目の前の資金繰りを安定させる必要がある。
今日もラインは稼働している。冷凍庫の中では、規格通りに成形された食品が次々と積み上がっていく。経営を支えるのは、日々の積み重ねと小さな工夫の連続である。目に見える利益よりも、止まらない現場の音こそが、この業界の真実を物語っている。
お寄せいただいた体験談は、お客様が特定できないことを目的に、若干の修正をしております。改変に当たり文章の意図は変えておりませんので、ご理解ください。