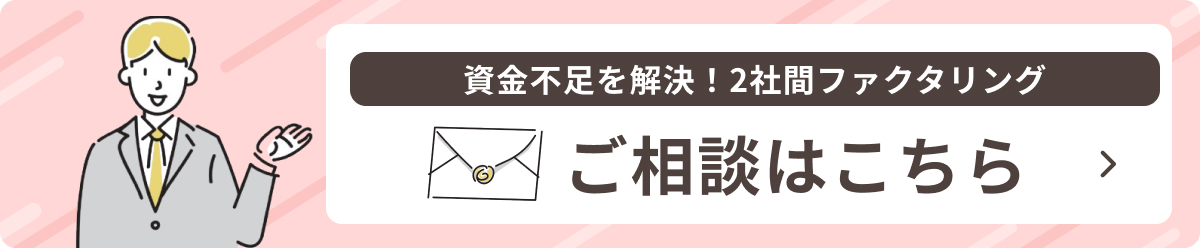ファクタリングは、企業が保有する売掛金をファクタリング会社に譲渡し、資金を早期に調達する手法であり、特に中小企業の資金繰り改善の手段として広く利用されています。その中でも「2社間ファクタリング」は、売掛先(取引先企業)を介さずに行われるため、利用しやすい一方で、不正行為が発生しやすい側面もあります。その代表例が「多重譲渡(重複譲渡)」です。本稿では、2社間ファクタリングにおける多重譲渡の実情と、その違法性について詳しく解説します。
- 2社間ファクタリングと多重譲渡の仕組み
2社間ファクタリングは、資金調達を希望する企業(以下「利用企業」)とファクタリング会社の間で契約が締結されます。通常、利用企業が保有する売掛金を1つのファクタリング会社に譲渡し、資金を受け取ります。しかし、多重譲渡とは、同じ売掛金を複数のファクタリング会社に対して譲渡する行為を指します。
多重譲渡は、以下のような形で行われることが一般的です。
1社目のファクタリング会社との契約
利用企業がA社に売掛金を譲渡し、資金を受け取る。
2社目のファクタリング会社との契約
既にA社に譲渡した同じ売掛金を、B社にも譲渡し、追加の資金を調達する。
売掛金の回収トラブル
売掛金の支払い期日になると、売掛先は通常どおり支払いを行うが、A社とB社のどちらが優先権を持つかでトラブルが発生する。このような行為は、短期間で多額の資金を調達できる反面、最終的に売掛金の弁済ができなくなるリスクが極めて高く、事実上の詐欺行為となる可能性があります。
- 2社間ファクタリングにおける多重譲渡の実情
多重譲渡は、特に資金繰りに行き詰まった企業によって行われるケースが多いとされています。以下のような背景が多重譲渡の温床となっています。
資金繰りの逼迫
経営が悪化し、銀行融資を受けられない企業が、ファクタリングを繰り返し利用するうちに、さらに資金が不足し、多重譲渡に手を染める。
2社間ファクタリングの構造的問題
2社間ファクタリングでは、売掛先が介在しないため、ファクタリング会社側が他のファクタリング契約の存在を確認しづらい。
ファクタリング会社の審査基準の甘さ
一部のファクタリング会社は、売掛金の譲渡状況を十分に調査せずに契約を締結することがあり、多重譲渡の発覚が遅れる。実際に、複数のファクタリング会社から資金を調達し続けた結果、支払いが滞り、最終的に倒産に至るケースも報告されています。
- 多重譲渡の違法性と法的リスク
多重譲渡は、民法および刑法において問題となる行為であり、以下のような法的リスクが伴います。
(1)民法上の問題
売掛金の二重譲渡は無効になる可能性
売掛金の譲渡契約は、先に登記(債権譲渡登記)または通知を行ったファクタリング会社が優先権を持ちます。
そのため、後から譲渡を受けたファクタリング会社は、売掛金の回収ができなくなる可能性が高い。(2)刑法上の問題
詐欺罪(刑法246条)に該当する可能性
売掛金を複数回譲渡することは、売掛金の実態を偽り、ファクタリング会社を欺いて資金を得る行為に該当するため、詐欺罪が適用される可能性がある。
詐欺罪が成立すると、10年以下の懲役が科される可能性がある。
横領罪(刑法252条)の適用もあり得る
売掛金が回収された際に、本来の債権者(ファクタリング会社)に返済せずに流用した場合、業務上横領罪が成立する可能性がある。(3)民事上の損害賠償責任
ファクタリング会社は、多重譲渡によって被った損害について、利用企業に対して損害賠償請求を行うことができる。- まとめと今後の対策
2社間ファクタリングの多重譲渡は、資金調達の選択肢が限られた企業にとって、一時的な資金繰りの改善策となるかもしれません。しかし、その実態は違法行為に直結しやすく、企業にとっても、ファクタリング会社にとっても大きなリスクを伴います。
今後の対策としては、以下のような取り組みが必要です。
ファクタリング会社による審査強化(売掛金の譲渡状況のチェック、登記の徹底)
売掛先への通知を推奨(2社間ではなく、3社間ファクタリングを活用する)
利用企業側の財務改善の努力(根本的な資金繰り対策を講じ、ファクタリングに依存しすぎない経営体制を構築する)違法な多重譲渡は、一時的な資金繰りの改善にはなっても、最終的には企業の信用を大きく損なう行為です。経営者としては、短期的な資金調達の手段だけでなく、根本的な経営改善に取り組むことが重要です。