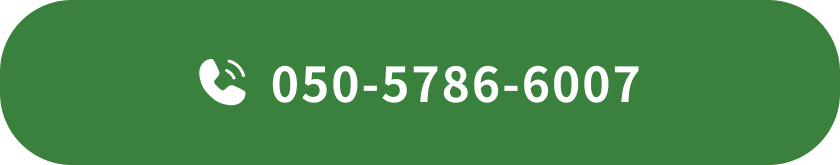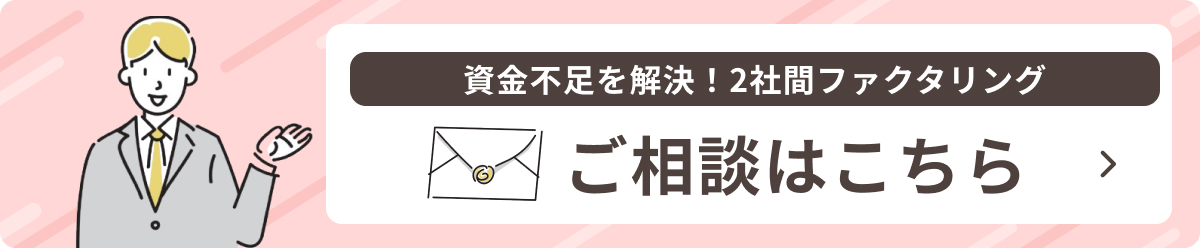私たちファクタリング業者が、日々最も注意を払っている法的な論点のひとつが「出資法第7条」および「貸金業法第2条第1項」による規制の及ぶ範囲です。特に、売掛債権を債権譲渡の形式で買い取る「二社間ファクタリング」の業務形態に対して、実質的には貸付けに該当するのではないかとの見解が、一部行政や学説において根強く存在しています。
まず、出資法第7条では「金銭の貸付けを業として行う者」が一定の利息制限を超えて金利を徴収した場合には刑罰が科されることが規定されています。さらに、貸金業法第2条第1項は、「金銭の貸付けを業として行う行為」を広く「貸金業」と定義し、同法第42条第1項では無登録でこれを行った場合の罰則が規定されています。
この点、ファクタリング契約は表面的には「売掛債権の売買契約」であり、あくまで金銭債権の売却によって資金を受け取る取引です。つまり、貸付けではなく、法的には売買契約として整理されるべきものです。しかし、問題となるのはその「実質」です。出資法・貸金業法の解釈においては、契約形式が売買であっても、「実質的に貸付けと同様の機能を有する」場合には、貸金業として規制の対象となり得るという考え方が存在します(いわゆる「実質貸付け論」)。
このような実質論の背景には、過去にファクタリングという名目で高利の貸付を行い、社会問題化した事例があることが挙げられます。とくに資金繰りに苦しむ中小企業に対して、ファクタリングを装いながら実態は貸付けであり、しかも手数料率が法定利息を大きく超えるような契約が多数発覚したケースがありました。こうした事案を受けて、金融庁や消費者庁の見解も厳しさを増し、実務上は「名を借りた貸金業ではないか」との視線が常に付きまとっています。
それでは、現在の私たちファクタリング業者は、この法的リスクにどう向き合っているのか。結論からいえば、契約の組成過程、実務運用、書類上の整合性、債権管理体制など、多方面にわたって「貸付けではない」という実体の構築を日々意識しながら運営しているのが実情です。
まず、契約書の記載内容については、売買契約としての形式を重視し、利息や元本返済といった貸金の性質を示す文言は一切使用していません。取引の対象が売掛債権であること、債権のリスクを当社が引き受けること、債権譲渡が有効に成立していることを、契約書類のなかで明確にしています。
次に、取引先企業の与信審査も、単に債務者(売掛先)の信用力だけでなく、売掛金が「真実存在しているか」「反復継続して発生しているか」「回収可能性が高いか」といった実務上の要素を確認しています。これは、売掛債権の適格性を見極めることで、単なる資金供与にならないようにするためです。
また、ファクタリング業者の立場として特に重要なのは、「償還請求権(リコース)」の有無です。二社間ファクタリングにおいては、買い取った債権が売掛先から回収不能となった場合、売主(利用者)に一定の責任を求めるケースがあります。これが強くなりすぎると、実質的に「貸付けと同じ」とみなされるリスクが増すため、弊社ではあくまで「買取契約」のスタンスを取り、利用者のリスクが限定されるように設計しています
とはいえ、完全なノンリコース(二者間での全リスク引き受け)を実現するのは難しく、たとえば売掛債権の不存在や不正が判明した場合には当然、売主に責任を求める規定は設けざるを得ません。このバランスこそが、法的なグレーゾーンとされている最大の理由です。
さらに、二社間ファクタリングにおいては、売掛先への通知を行わずに債権譲渡を成立させるため、債権管理や回収の実態が不透明になるケースもあります。これも「実質的に貸付けと変わらない」という評価の根拠となり得るため、弊社では譲渡登記や債権確認書などを通じて、譲渡の実体と意思表示を確保するように努めています。
最後に、制度整備への提言です。現在、ファクタリング業には明確な登録制度や監督官庁が存在しておらず、詐欺的な業者や悪質な高額手数料を取る業者が一部に存在することは否めません。私たちとしても、業界全体の信用を守るために、自主規制や標準契約書の普及、顧客への説明義務の強化などを推進する必要があると感じています。
将来的には、貸金業法の枠組みに準じた登録制度の導入や、ファクタリング専用の業法制定が議論される可能性もあります。その際、実質的に貸付けと異なる形態である「債権の流動化手段」としてのファクタリングが、健全な資金調達手段として社会に根づくためには、業者側が法的境界を自覚し、透明性と実体を伴った業務を継続していくことが求められます。