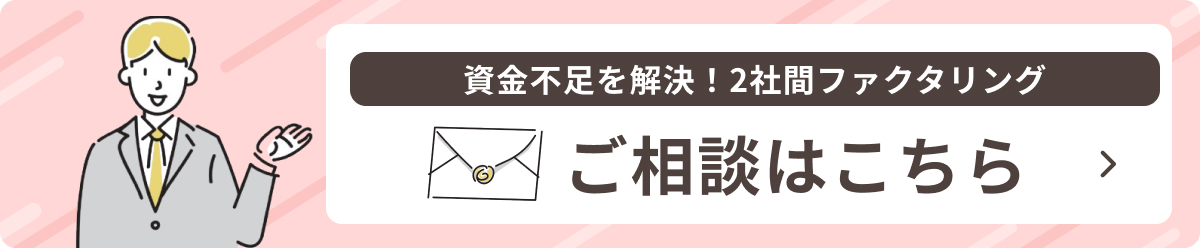これは、資金繰りに悩む中小企業や個人事業主にとって非常に重要な論点です。契約の内容次第で、単なる資金調達手段が、思わぬ法的リスクや経営上の負担へと変化する可能性があります。特に2社間ファクタリングにおいては、償還請求権の有無が「債権譲渡」と「貸金取引」の分水嶺になることがあり、慎重な検討が求められます。
償還請求権とは、売掛先(第三債務者)が支払い不能や支払い遅延などに陥った場合に、ファクタリング会社が債権の譲渡元である利用者に対し、譲渡代金の返還を請求できる権利を指します。つまり、ファクタリング会社が買い取った債権に関して、売掛先からの回収に失敗した際、その損失を利用企業に転嫁できる契約構造です。これに対して、償還請求権がない契約、すなわち「ノンリコース」契約では、ファクタリング会社は債権の買い取りと同時に回収リスクも引き受けるため、債権回収に失敗しても、利用企業に対して代金の返還を求めることはできません。これは、本来の債権譲渡の原則に近い考え方です。
問題となるのは、償還請求権が存在する契約が、形式上は債権譲渡であっても、実質的には貸付けと同等の構造になっている点にあります。
例えば、ファクタリング会社が債権の名義上の譲渡を受けるものの、売掛先への通知を行わず、さらに利用企業が回収業務を引き続き担うような契約形態では、ファクタリング会社は「債権譲受人」としてのリスクを負っておらず、単に資金を貸し出しているに過ぎないと評価される可能性が出てきます。
このような実態が明るみに出たのが、2020年に日本弁護士連合会が発表した意見書です。意見書の中では、償還請求権付きの2社間ファクタリングは、債権譲渡の体裁を取りながらも、貸金業法が規制する「貸付け」に該当する可能性が高いと指摘されました。とりわけ、債権回収の責任をファクタリング会社が負わず、利用企業が全て担うような形態では、経済的実態が「債権の売買」ではなく「融資」に近くなるという見解が示されました。
この見解は、実際の裁判例にも反映されています。東京地方裁判所や大阪地方裁判所などで取り上げられた事例において、売掛債権の名義がファクタリング会社に移転していたとしても、売掛先に対する債権譲渡の通知や債務者の承諾がないまま、回収業務が利用企業に委ねられていた場合、裁判所はその実態を貸付けと認定し、当該取引を無効または貸金業法違反と判断しました。
こうした判例は、今後のファクタリング実務に重大な影響を与えると考えられています。
償還請求権がある場合のリスクは、単に法律的な問題にとどまりません。経営実態の観点から見ても、資金繰りの改善を目的にファクタリングを利用したにもかかわらず、売掛先が倒産した場合などに、自らが支払責任を負うことになるため、当初想定していた「リスク移転」の効果が発揮されないという事態に直面します。これは、資金調達に伴う心理的・実務的負担が想像以上に重くなることを意味します。その一方で、ファクタリング会社側としては、償還請求権を設けることで、与信リスクを極力抑え、損失の発生を回避する意図があります
。特に、債権の真偽や回収可能性が不透明な中小企業や創業間もない事業者へのサービス提供においては、一定の安全弁を設けざるを得ないという現実的な事情があります。
このように、償還請求権は利用企業とファクタリング会社双方の利害が交差するポイントであり、単純に「ある・なし」で判断できるものではありません。重要なのは、その契約構造が法律に照らして問題ないか、また経営の健全性に資するものかどうかを、事前に十分に検討する姿勢です。
利用企業としては、契約前にファクタリング会社の説明を慎重に確認し、「償還請求権の有無」「売掛先への通知・承諾の有無」「回収業務の担当者」などの要素を総合的に判断することが求められます。必要に応じて、弁護士や税理士などの専門家に相談し、契約書の内容をリーガルチェックすることも重要です。
また、ファクタリング会社側においても、今後は形式的な債権譲渡にとどまらず、債権取得の実態を明確にし、契約書の文言だけでなく、業務運用の中身においても法的整合性を保つ努力が求められます。とくに、貸金業法の対象となる取引であれば、所定の登録を受け、適正な開示義務と運営体制を確保する必要があります。
ファクタリングは本来、売掛金の流動化によって資金繰りを改善し、事業継続をサポートする有効な手段です。しかし、その有効性を確保するには、単なる資金提供ではなく、法的にも経営的にも適正な仕組みとして成立している必要があります。
償還請求権の存在は、まさにそのバランスを左右する重要な要素です。資金を求める側も、提供する側も、短期的な利便性だけでなく、中長期的な安定性と法的リスクに対する理解を深めることが、これからのファクタリング実務における必須条件と言えるでしょう。