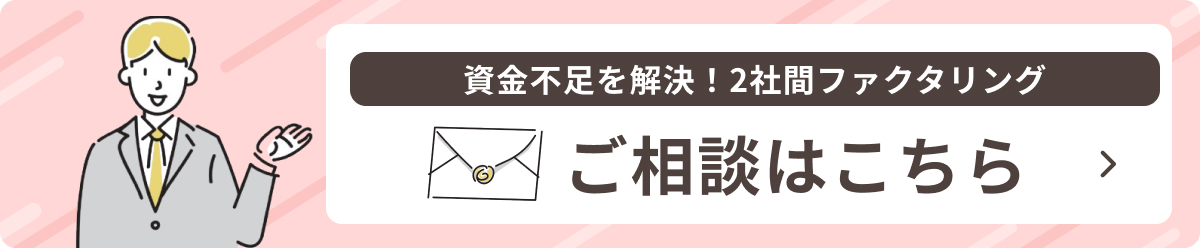資金繰りの手段として中小企業や個人事業主にも広く利用されるようになったファクタリング。その中でも「2社間ファクタリング」は、売掛先に通知せずに利用できる手軽さから、多くの現場で採用されています。
ただし、経理処理については独特の考え方が必要となり、初めて利用する場合には戸惑うことも少なくありません。本コラムでは、2社間ファクタリングに限定して、会計処理・仕訳例・税務上の注意点を解説します。
■ 会計上の考え方
2社間ファクタリングは、売掛金を表面上は譲渡しますが、会計上は「譲渡ではなく借入」とみなすのが通例です。そのため、仕訳処理では売掛金は残したまま、借入金や未払金といった負債科目で処理します。
ファクタリング手数料については、一般に損金算入され、「支払手数料」「雑費」などで処理されます。
■ 基本的な仕訳例
以下は実際の仕訳例です。
【前提】
売掛金:100万円
手数料:10万円(消費税不課税)
入金額:90万円① ファクタリング契約締結時(現金を受け取った時)
(借方)現金 900,000円
(借方)ファクタリング手数料 100,000円
(貸方)ファクタリング債務 1,000,000円
※ファクタリング手数料は「支払手数料」「雑費」「営業外費用」などの科目で処理できます。
② 売掛先からの入金をもって、ファクタリング会社へ支払った場合
(借方)ファクタリング債務 1,000,000円
(貸方)現金 1,000,000円
この一連の流れにおいて、売掛金自体の勘定科目は動かしません。あくまで「売掛金を担保に借入した」という経理処理の考え方です。
■ 決算書上の位置づけ
貸借対照表では、「ファクタリング債務」や「短期借入金」等として負債に計上されます。
財務内容に与える影響:負債が一時的に増加するため、自己資本比率の低下や銀行評価への影響が出ることがあります。
債務性があるか:実態としては債務性が強く、借入金と同様の注意が必要です。■ 税務上の取り扱い
◎ ファクタリング手数料の処理
手数料は損金算入が可能です。内容が事業に関連していれば、問題なく経費計上できます。
◎ 消費税の扱い
ファクタリング手数料は通常「非課税」となりますが、契約の内容によっては課税対象となるケースもあります。個別の契約書で消費税の記載があるかどうかの確認が必要です。
◎ 印紙税
通常、ファクタリング契約書には印紙税が発生しませんが、金銭消費貸借契約に近い性格を持つ場合、印紙が必要となる可能性もあります。契約書の書き方次第で取り扱いが変わるため、専門家の確認を受けるのが安全です。
■ よくあるミスと注意点
売掛金を帳簿から消してしまう誤り
2社間では売掛金は譲渡された扱いではなく、消さずに残します。ここを間違えると債権管理が混乱します。
仕訳が月をまたぐときの処理漏れ
ファクタリング契約と売掛金の回収が異なる月にまたがる場合、債務残高と現金収支がズレるため、処理のタイミングに注意が必要です。
決算書への記載漏れ
負債計上を忘れると、粉飾と取られるリスクがあるため、正しく明記することが求められます。■ まとめ
2社間ファクタリングの経理処理は、単純な売掛金の売却とは異なり、会計上は借入に近いものとして扱われます。仕訳処理においては、売掛金をそのまま残しつつ、「ファクタリング債務」として新たな負債を計上することになります。
また、ファクタリング手数料の損金処理、消費税の課税区分、決算時の開示義務など、細かい点でも誤解されがちな論点が多いため、事前に税理士や会計士と相談しながら処理を行うことが重要です。
適切な経理処理をすることで、資金調達としてのファクタリングを有効に活用でき、経営の安定につなげることが可能となります。