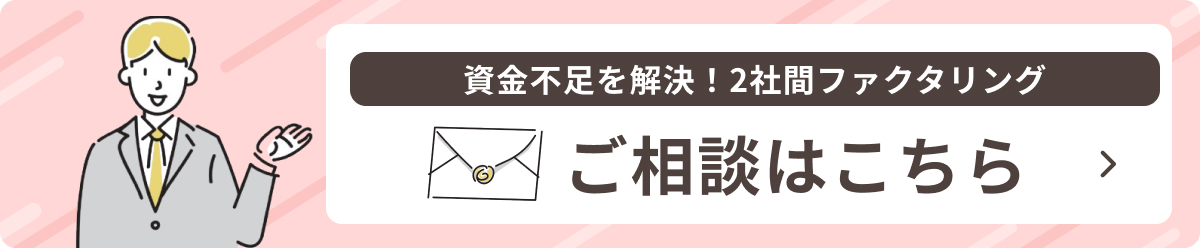事業者が資金調達の選択肢としてファクタリングを検討する際、必ずと言ってよいほど目にする言葉がある。それが「信用」である。「信用情報に傷があっても利用できます」「信用が大事です」といった文句が、広告やサービス紹介に並んでいる。しかしながら、この“信用”とは一体何を意味するのか。単なる個人の信用情報だけでは語れない、ファクタリング独自の“信用”の正体について、今回は掘り下げていきたい。
ファクタリングは、売掛債権を譲渡することで資金を得る取引である。銀行融資と異なり、担保や保証人を必要としない点が魅力であり、また、与信審査においても利用者本人よりも“売掛先の企業”に重点が置かれることが多い。ここにまず、ファクタリングにおける信用の特異性がある。
たとえば、ある中小企業がA社に対して100万円の売掛金を持っていたとする。この債権をファクタリング会社に売却して、早期に資金を手に入れたいと考えた場合、ファクタリング会社が注目するのは、その中小企業の経営状態だけではなく、「A社が確実に支払ってくれるかどうか」という点である。つまり、売掛先企業の「支払能力」「支払姿勢」が、もっとも大きな審査項目となる。
ここでの信用とは、“売掛先企業の信用力”のことである。具体的には、過去の支払遅延の有無、商業登記情報、企業規模、業歴、取引内容などから判断される。上場企業や大手企業であれば当然、信用が高いとされ、ファクタリングの審査もスムーズに通る傾向にある。一方で、売掛先が設立間もない企業や、支払いがルーズと知られている会社であれば、信用評価が下がり、買取不可とされることも珍しくない。
しかし、利用者側の信用がまったく見られないというわけではない。とくに2社間ファクタリングにおいては、売掛先に通知を行わないため、売掛債権の真正性を確認するうえで利用者の申告内容が重要になる。したがって、利用企業が過去に架空債権の譲渡を持ちかけた経歴がある、他社でもトラブルを起こしているなどの情報が共有されていれば、審査は非常に厳しくなる。
また、個人事業主やフリーランスの場合には、事業の透明性が乏しいこともあり、通帳の入出金履歴、契約書、請求書などから債権の実在性や継続性が評価される。これも一つの“信用”である。税金や社会保険の滞納がないか、反社会的勢力との関係がないかなど、コンプライアンスの観点からのチェックも行われる。
さらに言えば、ファクタリング会社によって“信用”の見方は少しずつ異なる。柔軟な審査をうたう業者は、売掛先の規模にさほどこだわらず、利用者の業歴や請求履歴から、一定の信用を見出そうとする。逆に、大手のファクタリング会社では、債権の回収可能性が最優先され、わずかでも疑義があれば否決となる場合もある。
一方で、世の中には「信用情報に傷がある方でもOK」といった広告を出している業者もある。たしかに、ファクタリングは貸金業ではないため、個人の信用情報(いわゆるCICやJICCなどのブラックリスト)は直接的には関係しない。だがこれは「信用が不要」という意味ではなく、「信用の種類が異なる」と捉えるのが正確である。
実際には、ファクタリングにおける“信用”とは、次の三つの要素が複合的に絡み合って成り立っている。
- 売掛先の信用力(支払能力・支払実績)
- 債権の真正性(請求書、通帳などによる裏付け)
- 利用者の信頼性(事業実態、反社チェック、過去の取引履歴)
この三つが揃ってはじめて、ファクタリング会社は「この債権なら買える」と判断することができる。逆に、売掛先が高信用でも、請求書がなかったり、通帳に入金の履歴がなかったりすれば、その債権は疑わしいとされ、審査に通らない。
最後に、“信用”とは単なる数値や点数ではなく、「信頼の積み重ね」によって形成されるものだという点を強調したい。ファクタリングを繰り返す中で、毎回、適切な書類を提出し、説明責任を果たすことで、利用者自身の“信用”も徐々に高まっていく。そしてその信用が、より有利な条件での資金調達へとつながっていくのである。
信用とは、金利や担保の代わりに問われる、もう一つの通貨のようなものだ。資金繰りの苦しいときこそ、その価値を見直すことが、事業継続の鍵となる。