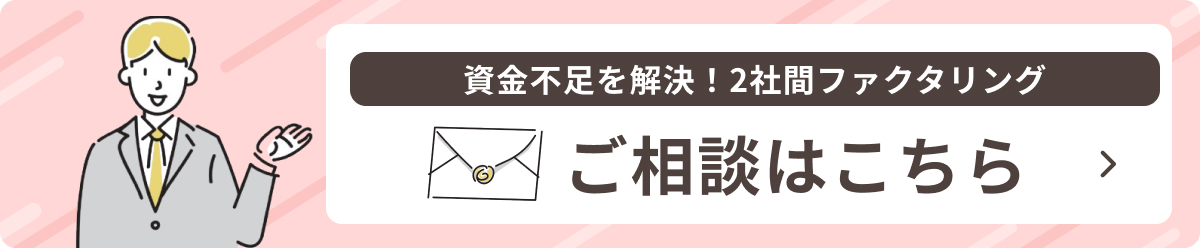一般的に契約書を作成する際、「公正証書にするべきか、それとも自分たちで書面を交わせば十分か」と考える方が少ないのが現状です。それは、公正証書について正しく知られていないことが、大きく影響しているのではないでしょうか。
「公正証書」とは、公証人という法律の専門職が、公証役場で作成する公文書のことです。契約当事者の合意内容を、法的に有効な形にするもので、特に金銭の支払いや損害賠償請求などについて「強制執行認諾条項」を盛り込めば、裁判を経ずに差し押さえが可能になります。
私的に作成した契約書と比べて証拠力が非常に高く、後々のトラブル防止に役立つのが特徴です。ここでは、「公正証書契約」と「公正証書にしない契約」の違いを具体的に掘り下げながら、それぞれのメリット・デメリット、そして利用すべき場面について解説していきます。
まず、最も基本的な違いは、「誰が作成するか」と「法的効力の度合い」にあります。公正証書契約は、公証役場にいる国家資格を持つ公証人が関与し、当事者の意思を確認したうえで作成されます。一方、公正証書にしない契約書、すなわち私的な契約書は、当事者同士が自由に内容を決め、文書化するものです。
公正証書の最大の特徴は、先にも書いた「強制執行認諾条項を盛り込むことで強制執行力がある」という点です。たとえば金銭の支払を約束する契約を公正証書にしておくと、万が一、債務不履行があっても、裁判を経ることなく、ただちに給与や預金口座の差し押さえなどの強制執行が可能になります。これは、債権者にとって非常に大きな安心材料になります。
反対に、私文書の場合、いくら署名や捺印がされていても、それだけで強制執行はできません。相手が約束を守らなかった場合、まず裁判を起こし、判決を得たうえで初めて強制執行に移ることになります。この手続きには時間も費用もかかりますし、精神的な負担も大きくなります。
もちろん、私的契約書が意味をなさないというわけではありません。契約内容が単純であったり、相手との信頼関係が厚かったりする場合には、あえて公正証書にしなくても問題がないケースもあります。また、公正証書を作成するには手数料がかかることもあり、簡単な物品の売買契約や日常的な業務委託契約であれば、通常の契約書で十分と言えるでしょう。
しかし、金銭が絡む契約、特に長期間にわたる分割払いの合意や、家賃滞納時の対応策、離婚にともなう養育費の支払い義務など、相手が不履行を起こすリスクが一定程度以上あるケースでは、公正証書を利用しておく方が圧倒的に迅速な対応ができます。契約違反が生じたとき、書面の効力がそのまま執行につながる点は、トラブルを未然に防ぐ抑止力にもなります。
さらに、公正証書は公文書となり、「高い証拠力を持つ」ことを意味します。万一、契約の存在や内容に争いが生じた場合、公正証書であれば裁判所もその信ぴょう性を高く評価します。一方、私的な契約書については、「本当にそのときの合意内容だったのか」「署名や印鑑は正当なものか」といった点が争点になりやすく、証拠としての信用度は公正証書ほどではありません。
また、公正証書には日付の証明力もあります。契約締結日が明確に公的に証明されるため、第三者に対して契約の存在を主張しやすいという利点もあります。たとえば、同じ物件に対する複数の賃貸契約があったような場合、公正証書の日付が確実な契約の順番を示す証拠になり得ます。
ただし、公正証書にも限界があります。
たとえば、違法な契約内容や、公序良俗に反する合意事項については、公証人が作成を拒否することがあります。また、強制執行可能な「強制執行認諾条項」が含まれていないと、いくら公正証書でもすぐに執行には移れません。
まとめ
公正証書契約は、その法的効力の高さと証拠力の強さから、将来的なトラブルを未然に防ぐための強力なツールと言えます。
一方で、費用や手間といったデメリットもあるため、すべての契約を公正証書にすべきとは限りません。契約の重要度、金額の大きさ、相手との関係性、そして将来のリスクの大きさを冷静に判断したうえで、必要な場面では積極的に公正証書を活用すべきです。