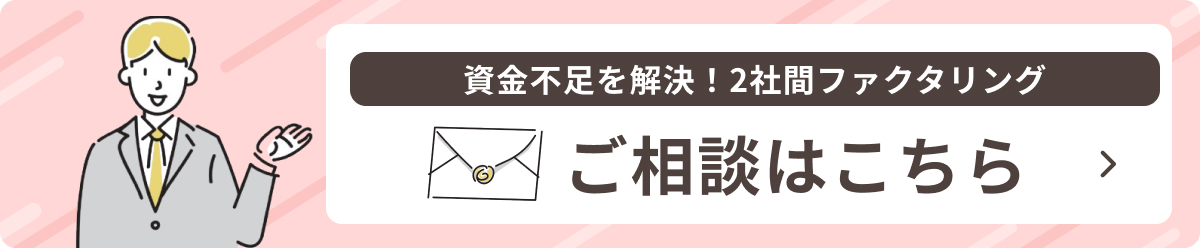中小企業庁が公表している『売掛債権の利用促進について』という資料は、資金調達手段の一つとして売掛債権の流動化を推進する目的で作成されています。その中では、債権譲渡による資金調達のメリットや、電子記録債権の活用、保証制度との連携などが紹介されており、金融機関をはじめとした関係者が中小企業の資金繰りを支援する仕組みの整備が進められています。
一方で、実務上よく用いられている「2社間ファクタリング」は、この制度的な枠組みとは異なる形で機能しており、整合性に疑問を持たれることも少なくありません。とくに法的な整理が不十分な中、債務者に通知しないまま第三者であるファクタリング事業者に債権が譲渡されるという構造については、制度側が前提としている「債権譲渡の透明性」や「債務者への明示」といった原則と衝突しやすい点が存在します。
本稿では、中小企業庁の政策的意図と、2社間ファクタリングの実務的な利用実態の間にどのような整合点と矛盾点があるのかを整理し、両者が今後どのように共存しうるかについて検討します。
売掛債権の利用促進政策の背景
『売掛債権の利用促進について』は、中小企業が保有する売掛債権を、信用力の補完的な役割として資金調達に活用することを促すものです。中小企業はしばしば、担保に供する資産が少ない、信用情報が十分でないといった理由で、金融機関からの融資が難しいとされます。そこで、売掛債権という「将来の資金獲得の確実性が高い資産」を活用することで、より多くの資金調達機会を与えようというのがこの施策の根本的な趣旨です。
たとえば、ABL(動産・債権担保融資)制度の拡充、電子記録債権の活用、保証制度との併用によるリスク低減などがその施策として挙げられています。これらの制度はいずれも「債務者への通知」や「債権譲渡の明確化」などを前提としており、債権の真正な譲渡と、それに基づく資金提供の安全性を重視する姿勢が貫かれています。
2社間ファクタリングの構造と実態
2社間ファクタリングとは、売掛債権の譲渡人(通常は中小企業)と、ファクタリング事業者の2者間のみで契約を締結し、債務者への通知や承諾を得ずに債権を譲渡する取引形態です。これにより、売掛先との関係に影響を与えることなく資金調達が可能になるため、特に下請企業などが取引継続に配慮する必要がある場合に重宝されています。
しかし、この取引にはいくつかのリスクや問題点が指摘されています。
- 債権譲渡の対抗要件が満たされないことによる二重譲渡のリスク
債務者に対する通知または承諾がなければ、第三者に対抗することができないため、債権の真正性や回収権限についてトラブルが生じる可能性があります。 - 「事実上の融資」との誤解・指摘
回収不能時の買取金返還条項や、売掛先の支払い能力に関する調査不足などがあると、売掛債権の「譲渡」というよりも「貸付」としての性質が強くなり、貸金業法違反とみなされるリスクもあります。 - 制度設計上の政策と乖離がある
通知や登記を前提とした公的制度との整合性に欠け、結果として制度側の透明性確保の方針と衝突するケースも少なくありません。
政策と実務の“すれ違い”
『売掛債権の利用促進について』では、債権の真正譲渡を前提とした透明性の高い取引を通じて、制度的な資金調達支援の幅を広げようとしていますが、2社間ファクタリングはその対極とも言える存在です。債務者に知らせないことで関係維持を優先し、対抗要件を備えないまま資金化するという構造は、本来制度が求める「公正性」とは対立しています。
しかし現実には、通知によって大口取引を失うリスクを避けたい中小企業が多く、あえて2社間を選ぶニーズが根強く存在しています。制度の理念と現場の現実の間には、単なる選択肢の違いでは済まされない「機能のギャップ」が存在すると言えるでしょう。
整合性を探る:規制と制度の間の落としどころ
中企庁の施策と2社間ファクタリングが両立し得るためには、単なる制度の拡充ではなく、「実務に即した透明性の確保」と「リスクの可視化」が必要です。
たとえば以下のような仕組みが考えられます。
- 事後通知型ファクタリングの制度化
取引時点では通知を不要としつつ、一定期間内に通知または記録を義務づけることで、債権の対抗要件を緩やかに担保するモデル。 - 電子債権記録制度との連携
譲渡された債権を電子記録債権として再構成し、ファクタリング事業者が記録機関に登録することで、第三者対抗要件と債権管理の透明性を同時に確保するアプローチ。 - 第三者保証または保険付きファクタリング
債権の支払不能リスクを保証会社が引き受けることで、実質的な回収不能リスクをヘッジし、譲渡の正当性を高める手法。
このように、現場のニーズに合わせた「中間的な仕組み」を制度側が受け入れることで、2社間ファクタリングの現実的な活用余地は広がります。一方で、ファクタリング事業者側にも、契約条項の透明化や、実質的な貸付とならないような構造の明示が求められます。
結論
中小企業庁の打ち出す『売掛債権の利用促進について』は、資金繰りの多様化を実現するうえで意義深い施策です。しかしその理念は、実務で広く行われている2社間ファクタリングとは部分的に齟齬があり、双方の「間」を埋める法制度や仕組みがいまだ不十分であることも否めません。
それでも、現実として多くの中小企業が2社間ファクタリングを必要としている以上、制度側は単に理想を押し付けるだけでなく、実務に寄り添った形での制度整備が求められる局面に来ています。透明性と実効性、そして現実的な利便性。その三点をどうバランスさせるかが、今後の政策形成における鍵になると言えるでしょう。