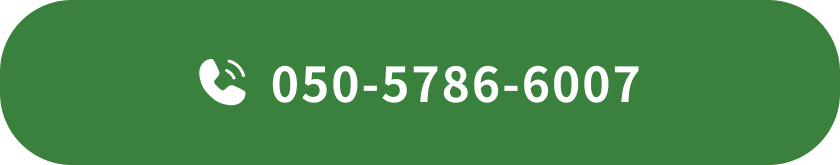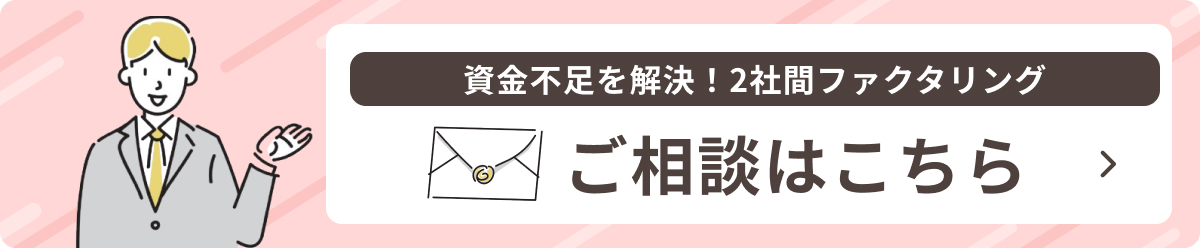2社間ファクタリングにおいては、登記によって債権譲渡の対抗要件を備えることが、債務者以外の第三者に対して権利を主張するための基本的な手続きとされています。ところが、現実の取引では、これだけでは不十分である場面が存在します。とくに、二重譲渡が発生し、先に譲渡された債権について別のファクタリング業者が公正証書をもとに債務者に対して執行を行っていた場合、登記を持つ後順位のファクタラーが回収できないというケースが起こりえます。
仮に、A社が同一の債権をB社とC社の2社に譲渡していたとします。B社は譲渡契約を公正証書化しており、A社が債務不履行に陥ったのを受けて、債務者に対して強制執行をかけました。一方で、C社はB社より後に債権を取得しましたが、登記を行っていたため、自らが真の債権者であるという主張をしています。
このような構図では、「登記をしていれば絶対に優先される」という理屈は、現実の執行場面において機能しなくなる可能性があります。すでに執行が終わり、金銭がB社に移転していた場合、C社がいかに法的な対抗要件を有していたとしても、その資金を取り戻すことは現実的には困難です。
さらにB社が契約を公正証書化していた場合には、「債権が真正に譲渡されたか」という問題の前に、「執行行為が手続き的に正当であったか」が先に問われます。B社が執行の過程で違法性なく回収を終えていたとすれば、B社は善意かつ適法に金銭を取得した第三者として保護される余地があり、C社の主張は後順位かつ実効性の乏しいものとして扱われる可能性が高くなります。
このとき、C社は真実の債権を譲渡されたにもかかわらず、回収できないという「存在しない債権を買わされた被害者」としての立場に置かれることになります。法的にはA社に対する損害賠償請求や契約責任の追及が可能であるものの、A社の経済状況が悪化していれば、事実上の泣き寝入りになるリスクが高いのが実情です。
つまり、登記は重要な対抗要件ではあるものの、それが実務上の安全保障として常に機能するとは限らないということです。とくに、公正証書に執行力が付されている場合には、登記という「紙の証拠」よりも、現場で実行される「金の動き」のほうが先行してしまうのです。このような構造的なリスクを踏まえれば、2社間ファクタリングにおいては、債権譲渡契約を締結するだけでなく、譲渡人との契約に以下のような条項を設けることが求められます。
債権の重複譲渡を明示的に禁止する条項
譲渡債権に係る瑕疵担保責任に関する明文化
既譲渡債権がないことを保証する表明保証条項また、C社としては譲渡を受ける際に、可能であれば債務者に対する通知または承諾を得ておくことが望ましいです。これにより、登記だけでなく実体面でも権利の安定性を高めることができます。
2社間ファクタリングはスピードと柔軟性が魅力ですが、その構造ゆえに潜在的リスクも多く抱えています。法的要件の形式的充足にとどまらず、実務上のトラブルを回避するための設計と運用が、ますます重要になってきています。