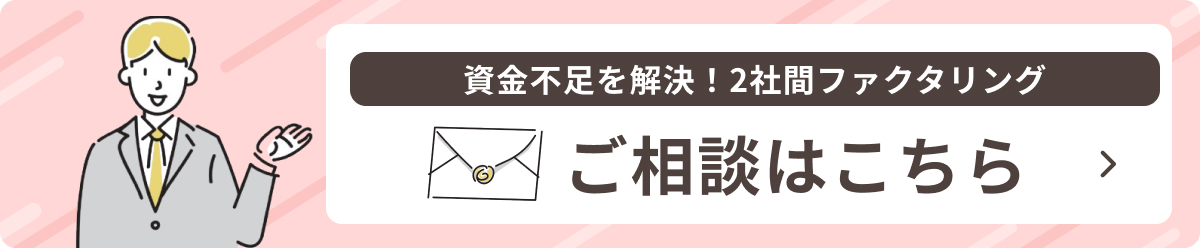ファクタリングとは、事業者が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却することで、早期に資金化できる手段です。本来は資金繰りを健全化させるための手段ですが、そこに「虚偽の債権」を持ち込む者がいた場合、事態は一転して重大な刑事事件に発展します。
中小企業の資金調達手段として広まりつつあるファクタリングですが、その制度を悪用して「実在しない取引先」「存在しない請求書」などをでっち上げ、金銭を詐取する行為=ファクタリング詐欺が全国で問題になっています。本コラムでは、架空債権によるファクタリング詐欺の法的評価と、具体的な処罰、さらには実際に起きた事例とその対処について解説します。
架空債権を使ったファクタリング詐欺の構造
まず、詐欺の典型的な手口を整理します。
架空の請求書(売掛債権)を作成する
→ 実際には取引をしていない相手先を装って請求書を作成します。
その請求書をファクタリング会社に提出し、債権譲渡契約を締結する
→ 譲渡通知や承諾書も偽造する場合があります。
ファクタリング会社から債権額に相当する現金を受け取る
→ 実際には取引がないため、当然、支払い期日が来ても入金はありません。
ファクタリング会社が債権先に連絡するか、入金がなかったことで詐欺が発覚する法的措置と適用される罪名
ファクタリングにおいて架空債権を用いた場合、以下のような刑事罰が適用される可能性があります。
- 詐欺罪(刑法第246条)
最も基本となるのが詐欺罪です。
他人を欺いて財物を交付させた場合、10年以下の懲役刑が科されます。
ファクタリング業者を騙して金銭を得た行為そのものが詐欺に該当します。たとえ返済の意思があっても、初めから取引実態がない以上、「人を欺く行為」に該当します。
- 私文書偽造・同行使罪(刑法第159条・161条)
取引先の承諾書や請求書などを偽造し、真正な文書であるかのように提示した場合は、私文書偽造及び行使罪が成立します。
この罪も、懲役1年以上10年以下と重い刑罰が科される可能性があります。
- 電磁的記録不正作出・供用罪
最近はすべてがデジタルでやり取りされているため、PDFの請求書や電子印鑑を偽造した場合には、電磁的記録に関する罪が問われることもあります。
民事上の責任
刑事責任とは別に、加害者はファクタリング会社に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。
ファクタリング契約は「債権の売買契約」であり、売主が無権利者(つまりその債権を持っていなかった)であれば、当然ながら契約は無効です。
損害賠償額としては、譲渡代金に加え、調査費・回収費・訴訟費用なども請求される場合があります。架空債権詐欺の具体例
【事例1】「個人事業者によるイベント会社名の悪用」
関東地方で、個人事業者が過去に一度仕事を請け負ったことのあるイベント会社の社名とロゴを無断使用し、「〇月分の設営作業代」として請求書を偽造。あたかも継続取引があるように装い、ファクタリング会社から約50万円を調達。イベント会社に照会が入り、架空取引と発覚。詐欺および私文書偽造・同行使で逮捕されました。
【事例2】「元取引先の名を騙って約300万円詐取」
別の事例では、実際に過去に取引があった工務店の名を使い、すでに関係が切れているにもかかわらず「〇月工事分」とする請求書をでっち上げ、300万円分の売掛金をファクタリング。第三債務者(取引先)への確認の際、相手側が否認したことで発覚。ファクタリング業者が刑事告訴し、本人は逮捕、執行猶予付きの有罪判決を受けています。
ファクタリング会社の対応と予防策
現在、ファクタリング業界では以下のような対応が進んでいます。
債権の**裏取り確認(債権の真実性調査)**の強化
第三債務者への譲渡通知や債権確認の義務化
取引先との契約書・発注書・納品書などの提出義務
反社チェックと合わせた信用調査の厳格化また、被害を受けたファクタリング会社は刑事告訴に踏み切る例が増えており、過去には被害額が少額でも警察に相談して告訴が受理された事例も報告されています。
詐欺に該当するか否かの線引き
「本当に存在していた債権だが、後にキャンセルとなった」
「取引先が支払いを渋っている」
「現場仕事を終えたが、まだ請求書を送っていない状態でファクタリングした」
こうしたグレーな状況でも、提出書類に偽りがあれば詐欺が成立する可能性は十分にあります。「だましてやろう」という明確な意図がなくても、「真実ではないと知りながら提出した」時点で違法性が問われます。
まとめ
ファクタリング制度は本来、事業者を支援するための柔軟な資金調達方法です。しかしその信頼性は、「債権の真実性」によって支えられています。これを意図的に崩すような行為、つまり架空債権の持ち込みは、単なる「未入金のリスク」では済まず、明確な詐欺犯罪として立件され、懲役刑にまで発展する重大な違法行為です。
一時的な資金難や焦りから、「バレなければいい」と安易に手を出してしまえば、事業そのものの信用を失い、人生の再起にも大きく影響します。資金繰りに苦しい時こそ、正規の手段で対応し、詐欺という取り返しのつかない道を選ばないことが、長い目で見たときに最善の選択と言えるでしょう。