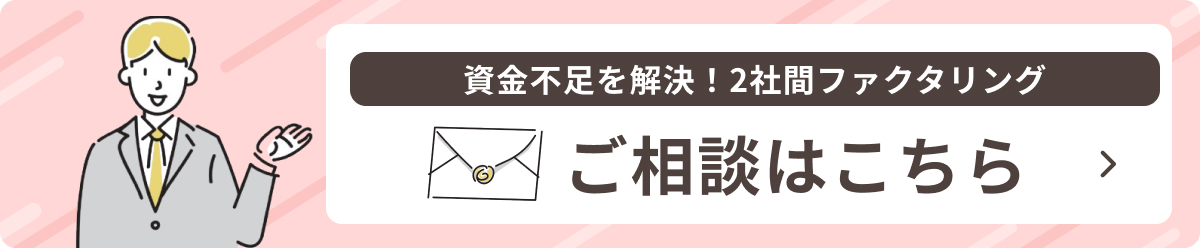2社間ファクタリングは、債権譲渡を行う売掛債権者(売渡人)とファクタリング会社の間で完結する仕組みであり、債務者(第三債務者)には債権譲渡の事実を通知せずに実施されることが多い。この特性ゆえに、売渡人が資金を受け取ったあとに売掛先からの入金をそのまま自社で回収し、ファクタリング会社に返済を行わないといった「回収委託金の流用」が問題となるケースが散見される。
本来、2社間ファクタリングでは、債権譲渡契約と同時に「債権回収業務の委託」が売渡人に課せられており、売掛金の入金を受けた場合は、その資金を遅滞なくファクタリング会社へ送金する義務がある。これを怠った場合、回収委託契約違反に該当し、債務不履行に基づく損害賠償請求が可能となる。
この損害賠償請求権は、実務上、契約時点からあらかじめファクタリング会社が取得し得るものとして定められていることもあり、仮に売渡人が返済を怠った場合には、ファクタリング会社はその損害賠償請求権を別の債権として設定し、それを第三債務者へ譲渡通知することがある。
つまり、ファクタリング会社は、本来の債権回収とは別に「売渡人に対する損害賠償請求権」という新たな債権を構築し、それを債権譲渡のかたちで第三債務者に通知し、債権の取立てを試みるわけである。ここで問題となるのが、第三債務者がこの請求に対して「自分には支払義務がない」として拒絶した場合である。
まず確認しておきたいのは、第三債務者とは、当初の売掛債権における債務者であり、原則としてファクタリング会社との間には直接的な契約関係が存在しない。したがって、損害賠償請求権がどのように譲渡されたかによって、支払義務の有無や正当性は大きく左右される。
このような状況において、第三債務者が支払いを拒む理由には、いくつかのパターンが考えられる。
第一に、「損害賠償債権の発生に納得できない」というものがある。つまり、ファクタリング会社と売渡人との間でどのような契約違反があったのか、第三債務者にとっては知る由もなく、自分が全く関与していない契約関係のトラブルに巻き込まれることに対する警戒である。この場合、債権譲渡通知が届いたとしても、その根拠が不明瞭であれば、支払いを拒むのは当然といえる。
第二に、「自分がもはや債務者ではない」とする抗弁である。売掛金をすでに支払済みである場合や、相殺などの処理によって債務が消滅している場合には、新たに譲渡された損害賠償債権に対しても当然に支払い義務が生じるわけではない。このような背景があれば、第三債務者は支払を正当な理由をもって拒絶できる。
第三に、「債権譲渡自体に無効の疑いがある」というケースである。損害賠償債権の性質や発生条件があいまいなまま、形式的に譲渡通知だけがなされた場合、債権譲渡が無効もしくは対抗力を欠いている可能性がある。この点についても、第三債務者は法的に争う余地がある。
こうした事態に直面したファクタリング会社は、次のいずれかの対応を取る必要がある。
まず考えられるのが、売渡人に対する直接請求の強化である。第三債務者からの支払いが得られない以上、損害賠償請求は本来の債務者である売渡人に向けて行うほかなく、法的措置(訴訟、強制執行など)による回収を図ることになる。これは最も確実なルートではあるが、売渡人に資産がなければ実効性に乏しい。
次に、「第三債務者に対する法的請求の可否」を精査する必要がある。損害賠償請求権が有効に譲渡されており、かつその根拠となる債務不履行が明確に示せるのであれば、第三債務者に対しても請求可能と判断されることがある。ただし、この場合、裁判所を通じた判断が求められる場面が多く、紛争化のリスクがある。
さらに、実務上では「債権譲渡登記」を活用して対抗要件を備え、譲渡の正当性を担保することも重要となる。登記によって譲渡の事実が客観的に証明されれば、第三債務者への請求の正当性もある程度補強されるため、支払い拒否への対応材料となり得る。
ただし、第三債務者との関係性を損なうリスクにも留意すべきである。ファクタリングの実施に際しては、売渡人と売掛先との信頼関係があって初めて成り立つビジネスモデルであり、債権譲渡が通知されることで商取引に悪影響が生じるケースもある。このため、多くのファクタリング会社では、2社間契約における通知の有無について慎重な対応を取っているのが現実である。
損害賠償請求の譲渡通知は、法的には可能であっても、実務上は取引先との関係や信用への配慮が大きく影響する。第三債務者が拒絶姿勢を示した場合には、訴訟リスクや風評リスクといった副次的な問題が生じるため、ファクタリング会社としても慎重な対応が求められる。
一方で、売渡人にとっても、回収委託金の流用は重大な契約違反であり、信用失墜や法的責任を招く行為であることを認識しておくべきである。資金繰りが逼迫していたとしても、委託された回収金は信託的な性質を持つものであり、流用によって一時的な資金繰りを凌いだとしても、結果として事業全体に大きな損失を与えるリスクがある。
このような構図において、2社間ファクタリングを活用する際には、売渡人・ファクタリング会社・第三債務者の三者それぞれが契約上の義務とリスクを正確に理解し、問題が顕在化した際にどのような対応が求められるかについて、あらかじめシミュレーションしておくことが重要である。