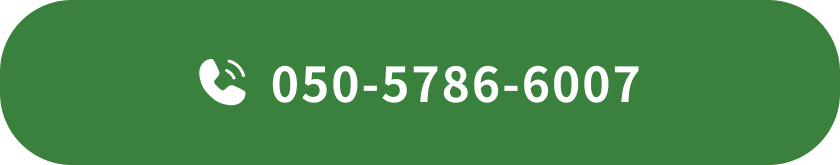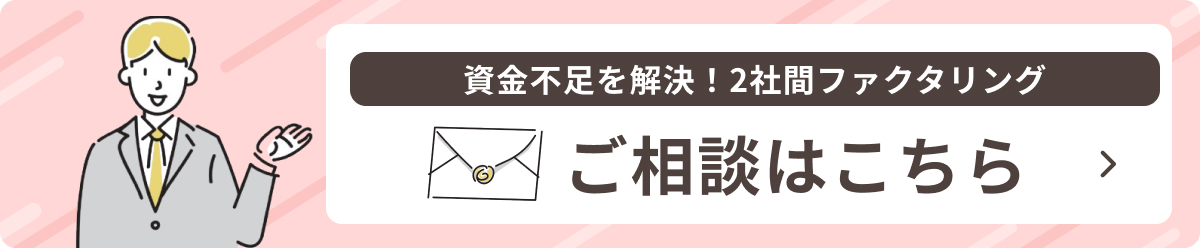刑事事件における詐欺罪の成立要件とファクタリング契約時の表明保証は、タイトルだけ見ると異なる分野に属するように思われますが、実務においては深く関連しています。特に、ファクタリング契約において虚偽の表明がなされた場合、民事的な損害賠償の問題を超えて、刑事責任が問われる可能性があるため、十分な理解が求められます。
■ 詐欺罪の成立要件(刑法246条)
刑法第246条は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と定めています。詐欺罪が成立するためには、以下の4つの要件が必要です。
欺罔行為(ぎもうこうい)
被害者の錯誤
財物の交付
因果関係と不法領得の意思
まず「欺罔行為」とは、相手をだます行為です。虚偽の説明や事実の隠蔽、誤解を与えるような発言などが該当します。次に、その欺罔行為によって被害者が誤信(錯誤)し、その結果として財物を交付してしまうことが求められます。そして、その欺罔行為と財物交付の間に因果関係があり、加害者に不法に他人の財物を得ようとする意思(不法領得の意思)があることが詐欺罪の成立には不可欠です。
■ ファクタリング契約における表明保証とは
ファクタリングとは、売掛債権を第三者に譲渡することで、早期に資金化を図る手法です。企業が資金繰りを改善する目的で活用されることが多く、銀行融資とは異なる資金調達手段として近年広く利用されています。
ファクタリング契約においては、債権の真実性、譲渡可能性、回収可能性などについて、債権譲渡人が様々な「表明保証」を行うことが一般的です。たとえば、以下のような項目が契約条項として盛り込まれます:
・債権が実在し、すでに発生していること
・債権に争いがなく、第三者に譲渡されていないこと
・支払期日に確実に履行される見込みがあること
・債務者に債権譲渡の事実が通知されていること(または通知義務を負うこと)
これらの表明保証が虚偽であった場合、民事上は契約解除や損害賠償請求の対象になります。しかし、内容によっては刑事上の責任、すなわち詐欺罪が問われるケースもあります。
■ 表明保証違反と詐欺罪の関係
例えば、債権譲渡人が実際には存在しない架空の売掛債権を譲渡し、対価として金銭を得た場合、これは典型的な詐欺罪の構成要件を満たします。
・欺罔行為:実在しない債権があると虚偽の申告をする
・錯誤:ファクタリング業者がそれを信じる
・財物の交付:金銭が支払われる
・不法領得の意思:実在しない債権により金銭を得ようとする意図
このような場合、民事上の契約違反にとどまらず、刑事事件として捜査・起訴される可能性が高くなります。また、債権が実在していたとしても、すでに二重譲渡されていたことを知りながら、別の業者に再譲渡する行為も、同様に詐欺罪の構成要件に該当し得ます。
■ 故意の認定と実務上の問題点
刑事事件として詐欺罪が成立するには、「故意」が必要です。つまり、譲渡人が虚偽であると知りながら欺罔行為を行ったことが証明されなければなりません。
この点で、単なる記載ミスや誤解、意思疎通の齟齬による誤った表明などがあった場合、直ちに詐欺罪に問うことは困難です。実務上は、契約書類、メール、メッセージ履歴などの証拠が詳細に検討され、「虚偽の事実を知りながら提供した」という意図が明確にされる必要があります。
■ 最近の事例と傾向
近年では、悪質なファクタリング利用者による詐欺的行為が社会問題となっており、警察・検察の関心も高まっています。実際、いくつかの事件では、債権の実在を偽ってファクタリング会社から数百万円単位の資金を不正に引き出したとして、詐欺罪での起訴が行われています。
こうした事件では、事業者側にとっても重大なリスクとなるため、ファクタリング会社は契約前の審査を厳格化し、売掛先へのヒアリングや通帳取引履歴の確認、請求書と納品書の整合性確認などを徹底しています。
■ まとめ
ファクタリング契約は、あくまで民事契約の一種ですが、契約時の表明保証に虚偽があった場合、それが重大な内容であれば刑事責任を問われる可能性があります。詐欺罪が成立するには、欺罔行為、錯誤、財物交付、不法領得意思の4要件に加え、「故意」の存在が必要ですが、意図的な虚偽であることが証明されれば、民事の枠を超えて刑事処分の対象となるのです。
ファクタリングを利用する事業者にとっては、契約における表明保証の重みを理解し、正確な情報を提供することが極めて重要です。また、ファクタリング業者側も、刑事リスクを回避するために、契約前の調査と表明保証違反時の対応を明確に定めておく必要があります。