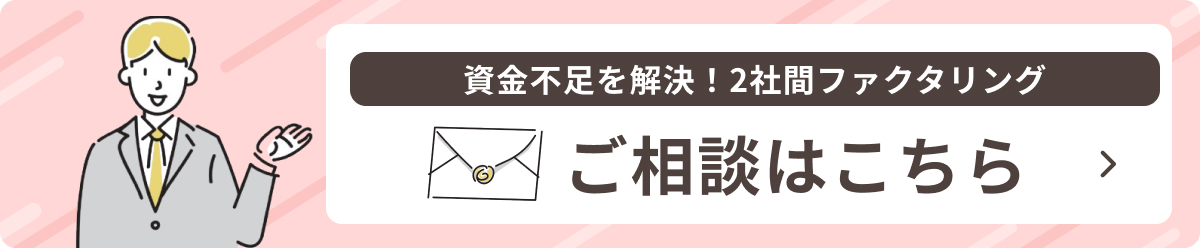ファクタリングは、本来、企業の資金繰りを支援する仕組みとして成り立っています。売掛債権を第三者に譲渡し、その対価として早期の資金を得ることで、支払いサイトの長い取引先との取引にも柔軟に対応できるという利点があります。特に2社間ファクタリングにおいては、取引先(債務者)に通知せずに行えることから、取引の継続性を維持しやすいという事情もあります。
しかし、この仕組みが「詐欺的に利用される」場面も散見されるようになってきました。つまり、実在しない売掛債権や、架空の取引に基づく債権をでっち上げ、それをファクタリング業者に譲渡することで資金を騙し取るという手口です。これが単なる民事的な不当原因給付にとどまるのか、それとも刑法上の詐欺に該当するのかという点は、非常に繊細かつ重大な問題です。
まず、ファクタリング取引において不正が行われる典型例を整理しておきましょう。
一つは、実際には存在しない売掛債権を提示し、ファクタリング契約を結ばせるパターンです。たとえば、既に支払済みの請求書や、存在しない取引先との架空の請求書を使い、「これから入金される予定の売掛金だ」として業者に売却するケースが挙げられます。
もう一つは、取引先の債務不履行を隠している場合です。つまり、債務者が既に倒産している、または支払い能力がないことを知っていながら、あたかも健全な債権であるかのように装ってファクタリングを行う行為です。
このような不正行為があった場合、契約そのものの原因が「虚偽」に基づいているため、民法上は「不当原因給付」(民法708条)として返還義務が発生する可能性があります。すなわち、売掛債権という給付の目的が虚偽である以上、それを受け取って資金化した側(譲渡人)は、その利益を返還する義務を負うことになります。
ただし、民事上の「不当原因給付」にとどまらないケースもあります。つまり、刑法上の「詐欺罪」に問われるかどうかという点です。
詐欺罪(刑法246条)は、「人を欺いて財物を交付させた者」に適用されます。ここで問題になるのは、「欺罔行為(ぎもうこうい)」と「財物の交付」の因果関係です。つまり、売掛債権の存在について故意に虚偽の説明を行い、その結果としてファクタリング業者が金銭を交付したのであれば、詐欺罪の構成要件を満たすことになります。
実際、裁判例においても、架空債権によるファクタリング取引に対して詐欺罪の適用が認められたケースは存在します。たとえば、全く取引のない架空の顧客を使って請求書を偽造し、ファクタリング業者から資金を得たケースにおいて、「取引実態が存在しないことを隠して資金を得たことは欺罔行為に当たる」として詐欺罪が成立しています。
また、ファクタリング業者が詐欺に加担していた場合、あるいは過失によって架空債権を見抜けなかった場合でも、基本的には譲渡人の詐欺責任を否定するものではありません。つまり、故意に売掛債権の不存在を知りつつ、それを事実であるかのように装って契約を締結させたのであれば、その行為自体が詐欺に該当します。
一方で、実際には売掛債権が存在したものの、その後の事情によって債務者からの入金が滞ったケースについては、直ちに詐欺とまでは言えないことが多いです。たとえば、売掛先の経営が急激に悪化した、債権回収に時間がかかっている等、客観的に見て債権譲渡当時には予見できなかった事情がある場合、詐欺の構成要件を満たすとは言いがたく、民事的な損害賠償にとどまる可能性が高いといえます。
また、「契約時にファクタリング業者が十分な審査を行っていたか」という点も重要です。つまり、業者側が明らかに審査を怠っていた、あるいは形式的な確認にとどまっていた場合には、一定程度の自己責任が問われる場面もあります。
そして、特に問題なのは「身元をくらまして逃げ回る」ようなケースです。こうなると、業者は譲渡人の所在を突き止め、訴訟を提起し、勝訴判決を得たうえで、強制執行の手続きに移る必要が出てきます。しかし、こうした場合でも、相手が資産を巧妙に隠していたり、別人名義の口座や会社を使っていたりすると、事実上の回収は困難になります。
こうした事態を未然に防ぐために、ファクタリング業者側では、譲渡人の信用調査、過去の売掛金回収実績、債務者との取引関係の継続性など、多方面にわたる調査を行う必要があります。そして、譲渡人側においても、ファクタリングの仕組みを誤解することなく、あくまで「債権の売却」であることを理解し、自身の説明に虚偽がないよう細心の注意を払う必要があります。
まとめ
結論として、ファクタリングにおける詐欺行為は、契約の性質や実態に応じて、民事上の不当原因給付にとどまるケースもあれば、刑事上の詐欺罪に発展するケースもあります。重要なのは、売掛債権という財産的権利の裏付けがあるかどうか、そして、それに関する説明に虚偽が含まれていないかという点です。
ファクタリングを正しく利用するためにも、その仕組みとリスク、そして責任の所在を明確に理解することが求められます。ビジネス上の「一時しのぎ」のつもりで虚偽を交えた結果が、重い刑事責任につながる可能性があることを、決して軽視してはいけません。