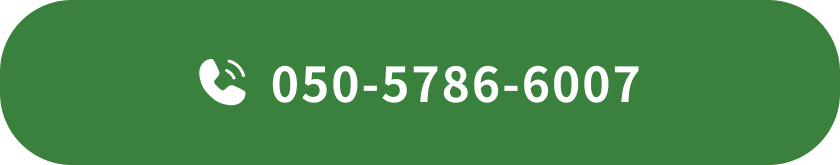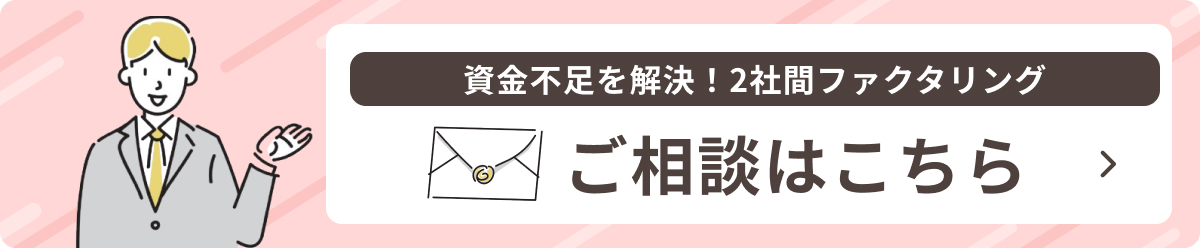企業経営において資金繰りは常に重要な課題であり、とりわけ中小企業にとっては、売上が立っていても回収までのタイムラグに苦しむ場面が少なくありません。売掛債権の回収までには通常30日から60日、多いところでは90日を要することもあります。そのような中で、資金化の手段として活用されているのが「ファクタリング」です。
ファクタリングとは、売掛債権を第三者(ファクタリング会社)に売却することで、期日前に現金を得られる仕組みです。資金繰りの改善策として即効性があり、融資とは異なり担保や保証人も不要な点が特徴です。特に、最近では銀行融資の審査が厳格化される傾向にある中、ファクタリングの利用が拡大しています。
しかし、このファクタリングと「与信管理」というテーマを考えたとき、そこには深いつながりがあることが見えてきます。
売掛先の信用が「商品」になるファクタリング
通常のファクタリングにおいて、審査の対象となるのは申込企業(利用者)だけではありません。むしろ最も重視されるのは、売掛先企業の信用力です。これは、ファクタリング会社にとって、将来的に確実に回収できる売掛債権かどうかを判断するうえで不可欠だからです。
売掛債権を商品と見立てるなら、その価値は「支払いが確実であること」によって決まります。たとえ利用企業の経営状況が苦しくとも、売掛先が上場企業であったり、長年安定した支払い実績がある場合、ファクタリング会社としては安心して債権を買い取ることができます。逆に、売掛先の信用が低い、または不透明な場合には、手数料が高くなったり、そもそも取引が成立しないケースもあります。
このことから、企業が日常的に行っている「与信管理」とファクタリングの相関関係が明確になります。
与信管理の目的と方法
与信管理とは、取引先に対してどの程度の信用(信用取引の限度額)を与えるかを管理する業務です。商品やサービスを提供したあとに代金を受け取る「掛け取引」が基本の商取引において、与信管理は債権回収リスクを防ぐための最前線です。
具体的には、次のような情報を収集・分析して判断します。
売掛先の決算書や登記簿情報
帝国データバンクや東京商工リサーチの信用調査報告書
支払遅延の有無や取引履歴
業界の動向や売掛先の商流こうした情報をもとに、取引限度額や与信期間を設定し、必要に応じて見直すのが一般的です。売上を増やすために与信を緩くすると、不良債権のリスクが高まります。かといって慎重すぎると商機を逃すことにもなるため、バランスが求められる業務でもあります。
ファクタリングは「与信の見直し機会」でもある
企業がファクタリングを利用する際、ファクタリング会社による「売掛先への与信審査」が必ず行われます。これは言い換えれば、第三者の目で自社の取引先の信用を評価してもらうことでもあります。
自社が気づかなかった売掛先のリスクが、ファクタリング会社の審査で明らかになることもあります。たとえば、支払いサイトが極端に長い、過去に支払い遅延がある、経営上の懸念があるなど、審査過程での指摘は自社の与信管理体制を見直すうえで貴重なヒントとなります。
また、ファクタリング会社とのやり取りを通じて、売掛債権の管理方法そのものを見直す契機にもなります。請求書の発行や送付、回収管理の体制が整っているか。取引契約書の有無や内容が明確かどうか。こうした基本的な管理体制が甘いと、ファクタリングの審査にも通りにくくなるため、自然と社内体制の改善へとつながります。
与信管理が甘い企業ほど、ファクタリング依存に陥りやすい?
与信管理が適切に行われていない企業は、売掛金の未回収リスクに日常的にさらされており、資金繰りに常に不安を抱えています。そうした中で、ファクタリングの即日資金化という利便性に頼りすぎると、必要以上に高い手数料を払い続ける状態に陥る可能性があります。
つまり、ファクタリングは与信管理の不備を埋める一時的な手段ではあっても、それ自体が恒常的な資金繰りの解決策にはなりえません。むしろ、与信管理がしっかりと行われている企業こそが、ファクタリングを「戦略的に使う」ことができるのです。
まとめ:ファクタリングと与信管理は表裏一体
ファクタリングは、単なる資金調達手段ではなく、「自社の売掛先の信用力」を見直す機会でもあります。売掛金という資産の価値を正しく理解し、日常的に適切な与信管理を行うことが、企業経営の安定には欠かせません。
そして、必要なときにだけファクタリングを選択肢として活用できる企業こそが、最終的に健全な資金繰りと成長のバランスを保てるといえます。
資金が足りないからファクタリング、ではなく、売掛金の「活用」と「管理」をセットで考えること。それが、ファクタリングと与信管理をめぐる本質的な課題であり、これからの時代に求められる視点だといえるでしょう。